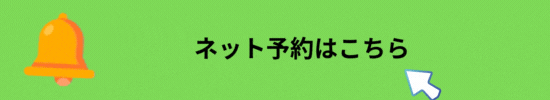目次
〜ご先祖様への想いがつなぐ未来〜
はじめに
法事とは、故人を偲び、家族の絆を再確認する大切な時間です。しかし、法事の本当の意味を深く理解し、心から納得して執り行っている人はどれほどいるでしょうか?
本書では、法事の本質と魚信の歩み、そして先代から受け継がれる想いを伝えながら、「ご先祖様を大切にすることが、豊かな人生の土台を築く」という視点を皆様にお伝えしたいと思います。
第一章:魚信の創業と成り立ち
魚信の歴史は、私の母・乃武子(のぶこ)が昭和42年5月、岡崎市岩津町のスーパーマーケットの一角に4坪の鮮魚店を開業したことから始まりました。
実は、私自身の誕生日が昭和42年4月26日。つまり、私が生まれた1週間後に創業したため、魚信の創業年数と私の年齢は完全に一致しています。
母は鮮魚店を営むだけでなく、自宅の2階をお座敷にして料理屋としても活用していました。仕入れた魚を余らせず、美味しい料理に仕立てて提供するという工夫は、当時から「本当にすごいアイディアだった」と今更ながら思います。
第二章:150人収容の大型店舗を創業した理由
昭和60年、鮮魚店を廃業し、現在の稲熊町に150人収容できる「味の集会場魚信」を開業しました。
先代がこの規模の店舗を創業したのには理由があります。単に空腹を満たすための飲食店ではなく、人が集い、笑顔で食事を楽しめる場を提供したいという想いがあったのです。
それは、単なる宴会の場ではなく、最も重視していたのは法事の後の食事処としての使命でした。
私の知る限りでは、祖母が特に先祖供養を大切にしていたことが、その背景にあると考えています。
第三章:受け継がれる想いと価値観
創業から58年、料理屋として40年が経過し、飲食業の在り方も時代と共に変化してきました。
しかし、おかげさまで今日も多くの地元の皆様にご支持いただいているのは、創業者である母の探究心と行動力の賜物です。
その根本には、「お客様に喜んでもらいたい」という気持ちが一番の原動力となっています。
また、魚信の料理は、祖業である魚屋としての強みを最大限に活かしながら提供してきました。新鮮な魚を扱い、その良さを最大限に引き出す手仕事。そこに、創業者の人柄がにじみ出ているのです。
そんな両親も、23年前に先代社長を送り、創業者である母・乃武子も一年前に見送りました。
しかし、私たちはこれからも、先代から受け継いだ「魚を中心とした地域の和食文化、日本の伝統文化」を大切にしていきます。
第四章:魚信の法事に対する想い
法事とは、ご先祖様への感謝の気持ちを形にする時間です。しかし、それは単なる儀式ではありません。
法事を通じて、私たちは家族とのつながりを感じ、これからの人生の在り方を考える機会を得ることができます。
そのため、魚信では法事の会食にも特別なこだわりを持っています。
- 天然にがり豆腐をはじめ、故人が好きだった料理を取り入れた特別な献立
- 落ち着いた個室で、家族が心を寄せ合える空間作り
- ご自宅での法事に対応した仕出し料理の提供
- 送迎バスの手配など、細やかな心遣い
法事の会食は、単なる食事の場ではなく、故人への供養の一環です。
料理を囲みながら故人の思い出を語り合うことで、心が癒され、新たな一歩を踏み出すきっかけにもなります。
魚信では、法事の席を「ただの食事の場」としてではなく、「故人との思い出を深め、未来への決意を新たにする場」としてお手伝いさせていただきます。
第五章:法事を通じて未来をつなぐ
私たちは、ご先祖様がいたからこそ今ここに生きています。
私たちの体の中には、数え切れないほどのご先祖様のDNAが宿り、その知恵や叡智が受け継がれています。15代さかのぼれば65,534人ものご先祖様が存在し、その一人でも欠けていれば、今の私たちは存在していません。
ご先祖様の命の流れが、今もなお私たちの心臓を動かし、生きる力を与えています。
日本には縄文時代という1万年にも及ぶ平和な時代がありました。その時代の人々の知恵や徳が、私たちのDNAの中に息づいているのです。ご先祖様は決して遠い存在ではなく、私たちの身体の中で今日も生き続け、未来へと命のバトンをつないでいます。
だからこそ、ご先祖様への感謝の気持ちを持ち、法事を通じてその想いを形にすることが大切なのです。
第六章:法事の基本知識とマナー
法事と法要の違い
法事とは、故人を偲ぶための仏教行事全般を指し、その中に読経を中心とした「法要」や、家族・親族が集まる会食などが含まれます。
各種法要の解説
- 初七日法要:故人が亡くなって7日目に行う最初の法要。
- 四十九日法要:故人の魂が成仏するとされる重要な節目。
- 一周忌法要:亡くなって1年目の節目となる法要。
- 三回忌、七回忌:その後も節目ごとに法要を営みます。
服装やマナー
法事では、故人を偲び、礼儀をもって参加することが大切です。
- 服装:基本は黒の喪服(男性はブラックスーツ、女性は黒のワンピースやアンサンブル)。
- 香典のマナー:金額の相場は法要の規模や地域によって異なりますが、一般的には5,000円〜30,000円程度。
- 会食(お斎)のマナー:静かに食事をしながら、故人の思い出を語り合う場として大切にします。